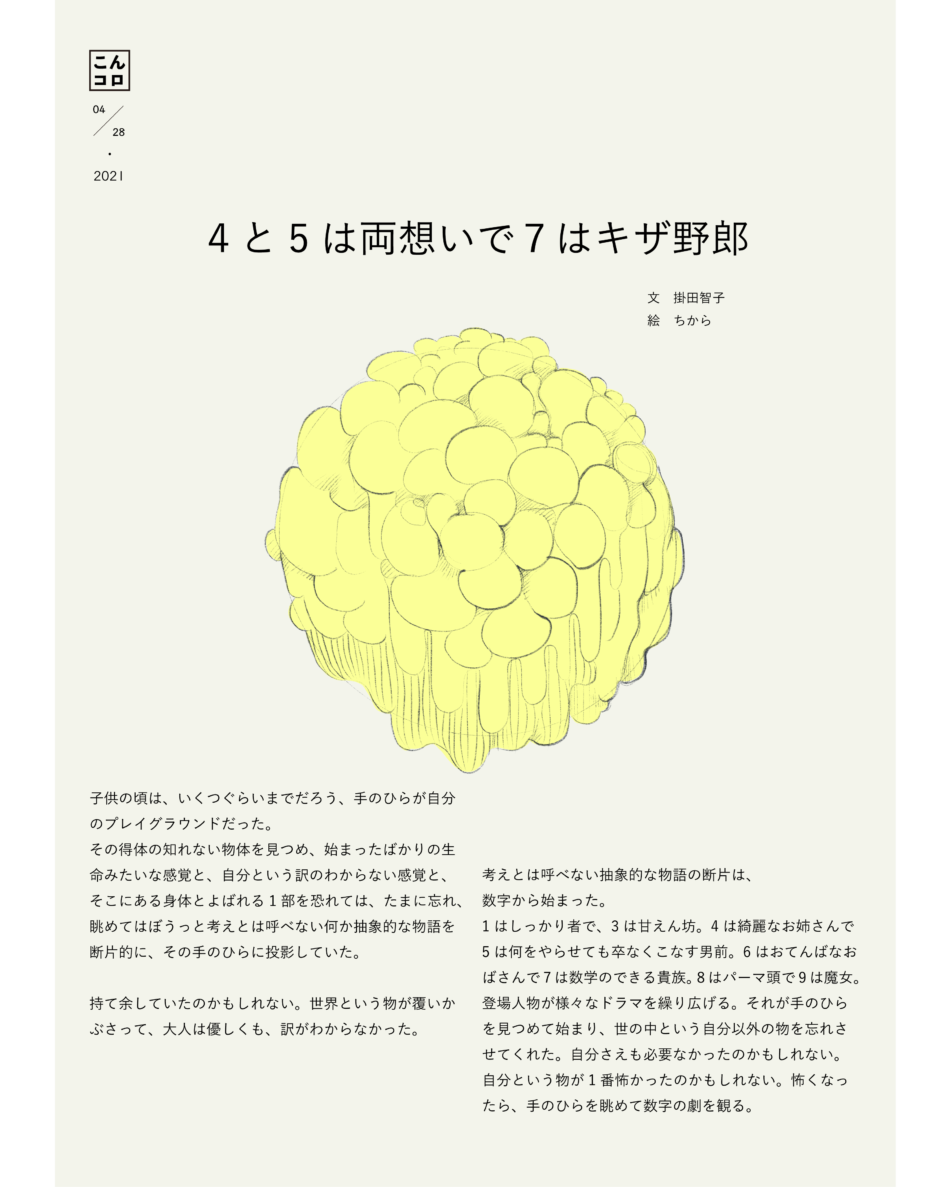
子供の頃は、いくつぐらいまでだろう、手のひらが自分のプレイグラウンドだった。
その得体の知れない物体を見つめ、始まったばかりの生命みたいな感覚と、自分という訳のわからない感覚と、そこにある身体とよばれる1部を恐れては、たまに忘れ、眺めてはぼうっと考えとは呼べない何か抽象的な物語を断片的に、その手のひらに投影していた。
持て余していたのかもしれない。世界という物が覆いかぶさって、大人は優しくも、訳がわからなかった。
考えとは呼べない抽象的な物語の断片は、数字から始まった。
1はしっかり者で、3は甘えん坊。4は綺麗なお姉さんで5は何をやらせても卒なくこなす男前。6はおてんばなおばさんで7は数学のできる貴族。8はパーマ頭で9は魔女。登場人物が様々なドラマを繰り広げる。それが手のひらを見つめて始まり、世の中という自分以外の物を忘れさせてくれた。自分さえも必要なかったのかもしれない。自分という物が1番怖かったのかもしれない。怖くなったら、手のひらを眺めて数字の劇を観る。
